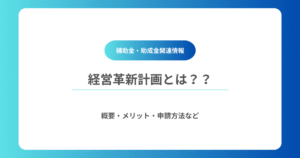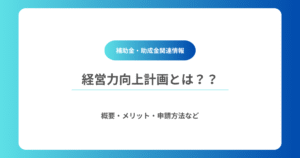【補助金採択率UP】一般事業主行動計画とは?
はじめに:なぜ今、一般事業主行動計画が中小企業に必要なのか?
現代の日本社会は、少子高齢化の進行、それに伴う労働力人口の減少という大きな課題に直面しています。このような状況下で、中小企業が持続的に成長を遂げるためには、多様な人材を確保し、その能力を最大限に活かすことのできる職場環境の整備が不可欠です 。こうした背景から、近年、従業員の仕事と家庭の両立支援や、女性の活躍推進などを目的とした「一般事業主行動計画」の策定・届出の重要性が高まっています。
特に2022年4月からは、法改正により、これまで努力義務とされていた常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の中小企業に対しても、この行動計画の策定・届出等が義務化されました。これは、多くの中小企業にとって、コンプライアンス対応という側面だけでなく、企業価値を高め、競争力を強化するための戦略的な取り組みとして捉えるべき重要な転換点と言えるでしょう。本記事では、この一般事業主行動計画について、中小企業が把握しておくべき概要、メリット、そして具体的な策定・届出方法に至るまで、網羅的に解説します。
一般事業主行動計画の基本:2つの法律と目的
「一般事業主行動計画」とは、特定の法律に基づいて企業が策定する行動計画の総称です。主に関連する法律は、「女性活躍推進法」と「次世代育成支援対策推進法」の2つであり、それぞれ異なる目的を持っていますが、多くの企業、特にリソースが限られる中小企業にとっては、これらの計画を一体的に策定し、運用することが推奨されています。
女性活躍推進法に基づく計画
女性活躍推進法(正式名称:女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)に基づく一般事業主行動計画は、女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活で活躍できる環境を整備することを目的としています [2, 3]。具体的には、採用、昇進等の機会の提供と積極的活用、職業生活と家庭生活の両立支援、そして職業選択における本人の意思の尊重といった点が重視されます 。この計画を通じて、企業は女性労働者の活躍を後押しし、ひいては人手不足の解消やイノベーションの創出といった効果も期待できます。
次世代育成支援対策推進法に基づく計画
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく一般事業主行動計画は、従業員が仕事と子育てを両立しやすい雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備に取り組むことを目的としています。この法律は、急速な少子化の流れを変え、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために制定されました。
両計画の一体的な策定について
これら2つの法律に基づく行動計画は、それぞれ異なる側面からのアプローチを求めていますが、中小企業にとっては、これらを別々に策定・管理することは事務負担の増加につながりかねません。幸いなことに、両計画の趣旨や求める取り組み内容には共通点も多く、厚生労働省も一体的な策定と届出を認めています。例えば、都道府県労働局への届出様式も、両法律に対応した一体型のものが用意されている場合があります。
中小企業がこれらの法制度に対応する際、事務負担の軽減は重要な考慮事項です。2つの法律に基づく計画を個別に作成・運用するのではなく、一つの行動計画として統合的に取り扱うことで、計画策定から届出、社内周知、進捗管理に至るまでのプロセスを効率化できます。これは、特に専門のHR部門を持たない、あるいは人員が限られている中小企業にとって、実務的なメリットが大きいと言えるでしょう。この一体的なアプローチは、単なる事務作業の簡略化に留まらず、企業全体として女性活躍と次世代育成支援を包括的に推進する戦略的な視点を持つことにも繋がります。
中小企業の義務と努力義務:自社は対象?
一般事業主行動計画の策定・届出・公表等の義務は、企業の常時雇用する労働者数によって異なります。特に2022年4月1日からの法改正で、対象範囲が拡大された点は中小企業にとって重要なポイントです。
従業員規模別の対応
- 常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の企業:
- 女性活躍推進法: 2022年4月1日から、一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部への公表、都道府県労働局への届出、そして数値目標を1つ以上設定することが義務化されました。また、自社の女性の活躍に関する情報(選択項目の中から1項目以上)を公表することも義務となります。
- 次世代育成支援対策推進法: 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部への公表、都道府県労働局への届出が義務付けられています。
- 常時雇用する労働者数が100人以下の企業:
- 女性活躍推進法・次世代育成支援対策推進法ともに: 一般事業主行動計画の策定、届出、公表等は「努力義務」とされています。
- 常時雇用する労働者数が301人以上の企業:
- 女性活躍推進法: 行動計画の策定・届出・公表に加え、数値目標を2項目以上(「職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立」の区分から各1項目以上)設定すること、そして女性の活躍に関する情報(選択項目の中から複数項目、男女の賃金差異を含む)を公表することが義務付けられています。
- 次世代育成支援対策推進法: 義務となります。
ここで言う「常時雇用する労働者」とは、正社員だけでなく、パートタイマー、契約社員、アルバイトといった名称にかかわらず、事実上継続して雇用されていると認められる労働者を含みます。具体的には、①期間の定めなく雇用されている者、②過去1年以上の期間について引き続き雇用されている者、または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者が該当します。この定義を正確に理解し、自社がどの規模に該当するかを把握することが第一歩です。
努力義務と戦略的活用
常時雇用する労働者数が100人以下の企業にとって、行動計画の策定は法律上の「努力義務」です。しかし、この「努力義務」を単なる努力目標と捉えるのではなく、企業成長のための戦略的な機会として活用することが可能です。なぜなら、行動計画を策定し、一定の基準を満たすことで得られる「くるみん認定」や「えるぼし認定」といった厚生労働大臣の認定制度は、義務対象でない企業も申請できるからです。これらの認定は、企業のイメージアップに繋がり、採用活動を有利に進めるだけでなく、後述する助成金の受給や公共調達における加点評価といった具体的なメリットにも結びつきます。したがって、100人以下の企業であっても、積極的に行動計画に取り組み、これらの認定を目指すことは、企業価値向上への有効な投資となり得るのです。
表1:中小企業の従業員規模別 義務早わかり表
| 従業員規模 | 女性活躍推進法に基づく計画 | 次世代育成支援対策推進法に基づく計画 | 主な義務内容(女性活躍推進法) |
|---|---|---|---|
| 100人以下 | 努力義務 | 努力義務 | 努力義務(状況把握・課題分析、数値目標設定、情報公表も努力義務) |
| 101人~300人 | 義務 | 義務 | 状況把握・課題分析(基礎項目から1つ以上)、行動計画策定・周知・公表・届出、数値目標1つ以上、女性活躍に関する情報公表1項目以上 |
| 301人以上 | 義務 | 義務 | 状況把握・課題分析(基礎項目4つ全て)、行動計画策定・周知・公表・届出、数値目標2つ以上(区分ごとに1つ以上)、女性活躍に関する情報公表3項目以上(男女の賃金差異必須) |
行動計画策定のステップ:何から始める?
一般事業主行動計画の策定は、大きく分けて以下の5つのステップで進められます:(1)自社の状況把握と課題分析、(2)行動計画の策定、(3)社内への周知と外部への公表、(4)都道府県労働局への届出、(5)取組の実施と効果測定。
ステップ1:自社の状況把握と課題分析
効果的な行動計画を策定するための最も重要な最初のステップは、自社の現状を正確に把握し、課題を明らかにすることです。
- 把握すべき項目例(基礎項目): 厚生労働省は、女性活躍推進法に関して、企業がまず把握すべき「基礎項目」を定めています。
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 男女の平均継続勤務年数の差異
- 労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
- 管理職(課長級以上など)に占める女性労働者の割合
常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の企業は、これらの基礎項目から少なくとも1つ以上を選択して状況を把握し、課題を分析する必要があります。301人以上の企業は、原則としてこれら4つの基礎項目全てを把握します。
- 課題分析の方法: 把握したデータをもとに、自社の課題を具体的に分析します。例えば、「女性の採用割合は高いが、平均勤続年数に男女差が大きい」という状況であれば、女性が出産・育児等を機に退職しやすい環境があるのではないか、といった仮説が立てられます。従業員アンケートやヒアリングを実施し、現場のニーズや両立支援制度の認知度、利用しづらい点などを把握することも有効です。分析した課題には優先順位をつけ、計画に盛り込むべき事項を絞り込みます。
ステップ2:行動計画の策定
状況把握と課題分析の結果を踏まえ、具体的な行動計画を策定します。計画には、以下の4つの要素を必ず盛り込む必要があります。
- 計画期間: 通常、2年間から5年間で設定します。自社の状況や目標達成に必要な期間を考慮して現実的な期間を設定することが重要です。
- 目標(数値目標を含む): 計画の達成度を客観的に測れるよう、具体的な数値目標を設定することが義務付けられています。
- 101人以上300人以下の企業は、女性活躍推進法に基づき1つ以上の数値目標を定めます。
- 301人以上の企業は、女性活躍推進法に基づき2つ以上の数値目標(原則として「職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立」の区分から各1つ以上)を設定します。
- 数値目標の例としては、「採用者に占める女性比率を〇%以上にする」、「管理職に占める女性比率を〇%以上にする」、「男女の平均勤続年数の差を〇年以下にする」、「従業員全体の残業時間を月平均〇時間以内とする」などが挙げられます。
この数値目標の設定は、単なる義務の履行に留まらず、中小企業が人事管理においてデータに基づいたアプローチを導入するきっかけとなり得ます。従来、感覚的に行われがちだった人事評価や制度設計も、具体的な数値を追いかけることで、より客観的かつ効果的なものへと進化する可能性があります。例えば、女性の採用比率や管理職登用率、勤続年数、時間外労働時間などを継続的に計測・分析することは、人事戦略の精度を高め、より的確な施策の立案・実行に繋がるでしょう。
ただし、目標設定にあたっては、男女雇用機会均等法に抵触しないよう注意が必要です。例えば、女性労働者を優先的に取り扱う目標は、雇用管理区分ごとにみて女性が著しく少ない(目安として4割を下回る)場合など、積極的改善措置(ポジティブ・アクション)として認められる一定のケースを除き、法違反となる可能性があります。 - 取組内容: 設定した数値目標を達成するために、どのような具体的な取り組みを行うのかを定めます。
- 例:女性採用拡大のため「会社説明会で女性が活躍できる職場であることを積極的にアピールする」、定着率向上のため「育児休業からの復職者に対する定期的な面談を実施する」「フレックスタイム制を導入する」、男性の育児休業取得促進のため「管理職向けに制度理解の研修を実施する」など。
- 実施時期: 各取組内容をいつからいつまで実施するのか、具体的な時期を明記します。これにより、計画の進捗管理が容易になります。
【コラム】厚生労働省提供のモデル行動計画活用術
厚生労働省は、企業の状況や規模に応じた様々な「モデル行動計画」をウェブサイトで公開しています。例えば、「女性の採用が進んでいない会社向け」「管理職の女性割合が低い会社向け」「残業が多く女性の離職率が高い会社向け」など、具体的な課題に対応したモデルが用意されています。中小企業が行動計画を策定する際には、これらのモデルを参考に、自社の実情に合わせて内容を修正・追加することで、効率的に計画を作成することができます。ただし、モデルをそのまま利用するのではなく、必ず自社の状況把握・課題分析の結果を反映させることが重要です。
ステップ3:社内への周知と外部への公表
策定または変更した行動計画は、速やかに社内外に知らせる必要があります。
- 社内周知: 正社員だけでなく、パートタイマーや契約社員など、雇用形態にかかわらず全ての労働者に周知します。周知方法としては、事業所の見やすい場所への掲示、イントラネットへの掲載、電子メールでの送付、書面での配布などが挙げられます。
- 外部公表: 策定した行動計画は、外部にも公表しなければなりません。公表方法としては、自社のホームページへの掲載や、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が一般的です。
ステップ4:都道府県労働局への届出
行動計画を策定または変更した場合は、「一般事業主行動計画策定・変更届」という様式を用いて、管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出ます。届出は、電子申請システム「e-Gov」を利用するほか、郵送または持参でも可能です。
ステップ5:取組の実施と効果測定
行動計画は策定して終わりではありません。計画に定めた取組を着実に実行し、定期的にその効果を測定・評価することが重要です。
- 取組の実施: 計画に沿って、具体的な施策を実行に移します。
- 効果測定と見直し: 数値目標の達成状況や取組内容の実施状況を定期的に点検し、必要に応じて計画内容を見直します。
- 女性の活躍に関する情報公表(継続的義務): 常時雇用する労働者数が101人以上の企業は、女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する状況について、定期的に(おおむね年1回以上)情報を公表する義務があります。公表する項目数は企業規模によって異なり、101人以上300人以下の企業は1項目以上、301人以上の企業は複数項目(男女の賃金差異を含む)の公表が必要です。
この一連のプロセス、特に効果測定と情報公表は、行動計画を一過性のものとせず、継続的な改善サイクル(PDCAサイクル)を回していくための重要な仕組みです。定期的な進捗確認と情報開示は、企業が自社の取り組みを客観的に評価し、より実効性の高い施策へと繋げていくことを促します。これは、中小企業が持続的に職場環境を改善し、多様な人材が活躍できる組織文化を醸成していく上で、非常に有効なアプローチと言えるでしょう。
一般事業主行動計画に取り組むメリット:企業価値向上と支援策
一般事業主行動計画の策定・実施は、単なる法的義務の履行に留まらず、企業に多くのメリットをもたらします。
人材確保・定着、生産性向上への効果
働きやすい職場環境の整備は、従業員の意欲向上に繋がり、生産性のアップが期待できます。また、出産や育児を理由とした退職を防ぐことで、貴重な人材の確保・定着率を高めることができます。特に労働力不足が深刻化する現代において、多様な人材にとって魅力的な職場環境を提供することは、企業の競争力を維持・向上させる上で不可欠です。
認定制度で企業のイメージアップ!
行動計画を策定し、一定の基準を満たした企業は、厚生労働大臣による認定を受けることができます。これらの認定は、企業の社会的評価を高め、採用活動や広報活動において大きなアドバンテージとなります。
- くるみん認定・トライくるみん・プラチナくるみん(子育てサポート企業):
次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組む企業が認定されます。男性の育児休業取得率の向上、柔軟な働き方の導入、所定外労働の削減などが認定基準に含まれます。
2022年4月からは、より多くの企業が取り組みやすくなるよう、認定基準が一部緩和された「トライくるみん認定」が新設されました。さらに高い水準の取り組みを行う企業には「プラチナくるみん認定」が付与されます。 - えるぼし認定・プラチナえるぼし(女性活躍推進企業):
女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良な企業が認定されます。評価項目(採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコース)の達成状況に応じて、3段階の「えるぼし認定」があり、特に優れた企業には「プラチナえるぼし認定」が付与されます。 - プラス認定(不妊治療と仕事の両立支援):
近年、不妊治療と仕事の両立支援の重要性が高まっていることを受け、「くるみんプラス認定」「えるぼしプラス認定」が創設されました。これらの認定は、通常のくるみん認定・えるぼし認定の基準に加え、不妊治療中の従業員に対する休暇制度の導入、柔軟な勤務体制の整備、相談窓口の設置といった支援策を講じている企業に与えられます。
これらの認定制度は、単一の基準ではなく、企業の取り組み段階や特性に応じた多様なレベルが設定されています。「トライくるみん」のような比較的手軽に取り組める認定から、「プラチナ」認定のような高度な水準を求めるもの、さらには「プラス」認定のように特定の課題に特化した支援を評価するものまで、段階的かつ多角的な評価軸が存在します。この階層的な認定システムは、中小企業が自社の状況に合わせて目標を設定し、ステップアップしていくことを可能にします。最初は基本的な認定を目指し、徐々により高度な取り組みへと進むことで、継続的な職場環境改善のモチベーションを維持しやすくなります。また、「プラス」認定の登場は、社会のニーズの変化に応じて、企業に求められる支援のあり方も進化していることを示しており、企業が時代の要請に応じた先進的な取り組みを行うインセンティブともなります。
中小企業が活用できる助成金制度(くるみん助成金など)
特に中小企業にとって魅力的なのが、認定取得に伴う助成金制度です。
- くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業):
常時雇用する労働者数が300人以下の中小企業が、「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」のいずれかを受けると、助成金の対象となる可能性があります。
助成額は、1事業主あたり上限50万円(プラチナくるみんの場合は毎年度申請可能)で、育児休業取得者の代替要員の賃金、事業所内保育施設の設置・運営費、テレワーク導入費用、両立支援のための研修費用などが対象経費となります。申請は「くるみん助成金ポータルサイト」を通じて行います。この助成金制度は、中小企業が仕事と子育ての両立支援策を導入・運用する際の経済的負担を直接的に軽減するものです。多くの SMEs が直面する予算やリソースの制約を考慮し、代替要員の確保やテレワーク環境整備といった具体的な費用を補助することで、次世代育成支援対策推進法の趣旨に沿った取り組みを財政面から後押しします。これにより、認定取得を目指すことが、単なるイメージアップだけでなく、実質的なコスト負担の軽減にも繋がり、中小企業が積極的に行動計画を推進する強い動機付けとなります。
- その他、女性活躍推進に関連する設備投資(女性専用トイレや更衣室の設置など)に対する助成金制度も存在する場合があります。
公共調達での加点評価と融資優遇
- 公共調達: 「くるみん認定」や「えるぼし認定」を受けた企業は、国や地方公共団体などが行う公共調達の入札において、加点評価を受けられる場合があります。これは、受注競争において有利に働く可能性があります。内閣府や財務省も、このような取り組みを推進しています。案件によっては、技術点や企画点の5%~10%相当の配点がなされることもあり、競争力の強化に繋がります。
- 融資優遇: 認定企業は、日本政策金融公庫などの金融機関から、通常よりも低い金利で融資を受けられる制度を利用できる場合があります。
表2:主な認定制度とメリット一覧
| 認定制度名 | 対象法律 | 主な目的 | 中小企業の主なメリット |
|---|---|---|---|
| くるみん認定 | 次世代法 | 子育てサポート | ロゴ使用、くるみん助成金(300人以下)、公共調達優遇、低利融資 |
| トライくるみん認定 | 次世代法 | 子育てサポート(導入段階) | ロゴ使用、公共調達優遇、低利融資 |
| プラチナくるみん認定 | 次世代法 | 高水準の子育てサポート | ロゴ使用、くるみん助成金(300人以下、毎年度)、公共調達優遇、低利融資 |
| えるぼし認定(1~3段階) | 女性活躍法 | 女性活躍推進 | ロゴ使用、公共調達優遇、低利融資 |
| プラチナえるぼし認定 | 女性活躍法 | 高水準の女性活躍推進 | ロゴ使用、公共調達優遇、低利融資 |
| くるみんプラス認定・プラチナくるみんプラス認定 | 次世代法 | 子育てサポート+不妊治療両立支援 | ロゴ使用、くるみん助成金(300人以下)、公共調達優遇、低利融資 |
| えるぼしプラス認定 | 女性活躍法 | 女性活躍推進+不妊治療両立支援 | ロゴ使用、公共調達優遇、低利融資 |
中小企業が抱えがちな課題と解決のヒント
一般事業主行動計画の策定・運用にあたり、中小企業は特有の課題に直面することがあります。しかし、これらの課題には解決のヒントや利用できる支援策が存在します。
何から手をつければ良いかわからない
多くの中小企業では、専門の人事担当者がいない、あるいは法制度に関するノウハウが不足しているといった状況が見られます。
- 解決のヒント:
- まずは、自社の従業員規模を確認し、法的義務の有無や内容を正確に把握することから始めましょう(本記事の表1参照)。
- 厚生労働省が提供している「モデル行動計画」や策定支援ツールを活用することで、計画策定の具体的なイメージを掴むことができます。
- 最も重要なのは、ステップ1で解説した「自社の状況把握と課題分析」です。現状を客観的に把握することで、取り組むべき課題が明確になり、計画の方向性が見えてきます。
リソースが限られている中での計画運用
予算や人員が限られている中で、新たな取り組みを進めることに困難を感じる中小企業は少なくありません。
- 解決のヒント:
- 全ての課題に一度に取り組もうとせず、分析結果に基づいて優先順位をつけ、最も影響の大きいと思われる課題から着手しましょう。
- 初期投資を抑えられる施策(例:既存制度の周知徹底、意識啓発のための研修、ノー残業デーの設定など)から始めるのも一つの方法です。
- 「くるみん助成金」のような助成金制度を積極的に活用し、経済的な負担を軽減しましょう。
- 行動計画の管理や進捗確認を、既存の会議や業務プロセスに組み込むことで、新たな負担を最小限に抑える工夫も考えられます。
相談窓口と支援サービスの活用
行動計画の策定や運用に関して、中小企業が利用できる相談窓口や支援サービスは多数存在します。これらのリソースを積極的に活用することで、専門的な知見がない、あるいはリソースが不足しているといった課題を補うことができます。
- 主な相談窓口・支援サービス:
- 都道府県労働局雇用環境・均等部(室): 行動計画の届出先であると同時に、制度に関する相談にも対応しています。
- 次世代育成支援対策推進センター: 厚生労働大臣が指定する団体で、一般事業主行動計画の策定・実施に関する相談や援助業務を行っています。
- 厚生労働省のウェブサイト: 「両立支援のひろば」や女性活躍推進法特集ページなど、関連情報、Q&A、各種様式などが掲載されています。モデル行動計画もこちらから入手可能です 。
- 中小企業基盤整備機構(SMRJ): 経営相談や人材育成支援など、中小企業向けの幅広い支援メニューを提供しており、行動計画策定に関連する人事労務管理の相談にも応じてもらえる可能性があります。
- 社会保険労務士(社労士): 人事労務管理の専門家であり、行動計画の策定から運用、助成金申請まで、具体的なアドバイスや実務サポートを受けることができます。
このように、国や関連機関は、中小企業が行動計画に関する義務を履行し、さらにそれを企業価値向上に繋げられるよう、多岐にわたる支援体制を整備しています。モデル計画の提供から、専門家による個別相談、さらには経済的負担を軽減する助成金制度まで、これらのサポートを上手く活用することで、中小企業はリソースの制約を乗り越え、効果的に取り組みを進めることが可能です。これは、単に規制を課すだけでなく、その達成を後押しする社会的な仕組みが整えられていることを意味し、企業が前向きに行動計画に取り組むための一助となるでしょう。
まとめ:未来志向の経営へ、はじめの一歩
一般事業主行動計画の策定と実践は、法改正によって多くの中小企業にとって喫緊の課題となりました。しかし、これを単なるコンプライアンス対応と捉えるのではなく、自社の未来を形作るための戦略的な投資と位置づけることが重要です。
少子高齢化と労働力不足が進行する中で、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる魅力的な職場環境を構築することは、企業の持続的な成長に不可欠です。女性活躍推進や仕事と育児の両立支援は、従業員の満足度とエンゲージメントを高め、生産性の向上、イノベーションの創出、そして優秀な人材の獲得・定着に繋がります。
行動計画の策定プロセスは、自社の人事戦略や職場環境を見つめ直し、課題を明確にする良い機会となります。そして、その課題解決に向けた具体的な取り組みは、従業員エンゲージメントの向上、企業イメージの向上、さらには助成金や公共調達での優遇といった実利的なメリットをもたらします。
本記事で解説したステップや支援策を参考に、まずは自社の現状把握から始めてみてください。一般事業主行動計画への取り組みは、変化の激しい時代において、企業がより強く、より魅力的な組織へと進化するための、未来志向の経営への確かな第一歩となるはずです。